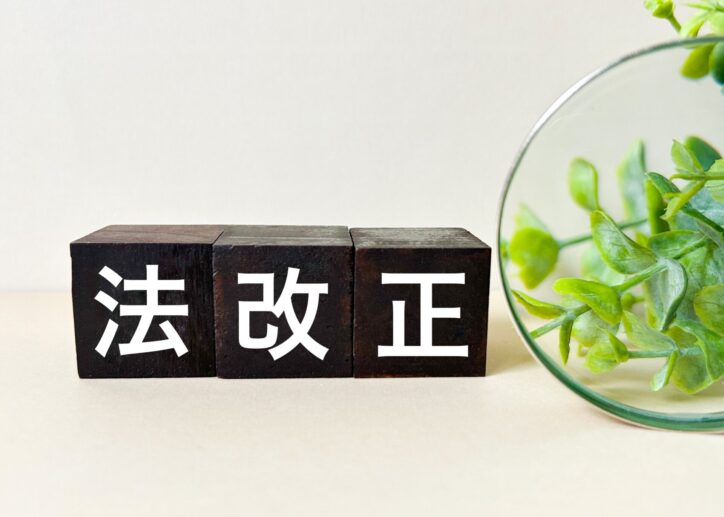排煙設備は、火災発生時に大量に発生する煙を屋外に排出させることで、人命や避難を助ける重要な役割を果たします。
この記事では、万が一火災が起こった際に必要な排煙設備について詳しく解説します。
具体的には以下の3点です。
・排煙設備の具体的な役割
・設置が必要な建物や設置の条件
・義務づけられている点検の内容
排煙設備に関する正しい知識を身につけ、建物の防災管理・安全管理を徹底しましょう。
定期報告(特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備検査)特設ページはコチラ
排煙設備とは?役割や必要な理由
排煙設備とは、火災が起こった際に発生する煙や有毒ガスを屋外に迅速に排出させ、避難や消火活動を助ける、窓や機械設備の総称です。
排煙設備が火災時に果たす役割は、以下のとおりです。
・火災の初期からフラッシュオーバーによる火災の拡大を遅らせる
・避難経路に煙やガスが充満することを抑える
・一酸化炭素や有毒ガスによる人的被害を防ぐ
・煙やガスを排出して避難を容易にすると同時に消防活動を円滑にする
| ※フラッシュオーバー:火災時に室内の局所的な火災が、数秒から数十秒の短時間で部屋全体に拡大する現象 |
火災時に発生する煙は視界を遮るだけでなく、一酸化炭素や有毒ガスを含むため、命に関わるほどの脅威です。
実際、総務省消防庁「令和4年版消防白書」によると、火災による死因の多くは、火傷に次いで煙の吸引による一酸化炭素中毒・窒息とされています。
排煙設備が煙を効果的に屋外に出して避難経路を確保できることで、迅速かつ安全な避難が可能になるのです。
さらに、消防隊の視界不良と高温環境を改善し、消火・救護活動を助ける重要な役割があります。
排煙設備は2種類
火災は炎だけでなく、煙も危険な要因であることは前述したとおりです。
排煙設備だけで火を消すことはできませんが、適切に作動することにより被害を最小限に抑えられます。
ここでは、排煙設備の種類やそれぞれの違い、使い分けについて解説します。
具体的には下記のとおりです。
・自然排煙設備
・機械排煙設備
・自然排煙設備と機械排煙設備の違いと使い分け
順に説明します。
自然排煙設備
自然排煙設備とは、室内の天井付近に設けられた排煙口や排煙窓により、火災時に煙を屋外に排出する設備です。
煙が自然に上へと昇る性質を利用して、自然の力で煙を外へ逃がします。
電力が不要なため、停電時でも使用できます。
しかし、外部の風や室内の温度によって排煙率に影響を受ける点や、外部に接している部屋でしか使えない点はデメリットです。
機械排煙設備
機械排煙設備とは、火災時に発生する煙を機械を使って屋外に強制的に排出する設備です。
煙を感知すると自動的に排煙口が開き、ダクトを通して煙を外に放出します。
外の風や室内外の温度に左右されることなく安定した排煙が可能です。
ただし、停電を想定した予備電源の確保や、排煙の導線となるダクトの設置・定期的なメンテナンスが必要です。
機械排煙設備には、以下のような方式があります。
| 排煙口方式 | 煙を感知すると自動的に煙を外に排出する最もポピュラーな方式 |
| 加圧排煙方式 | 排煙口方式と並行して、火災がまだ発生していない場所に新鮮な空気を送り込む方式 |
| 天井チャンバー方式 | 天井チャンバーという煙を一時的に蓄積するスペースを作り、そこから煙を吸い込んで外に排出する方式 |
自然排煙設備と機械排煙設備の違いと使い分け
自然排煙設備と機械排煙設備の主な違いは、下表のとおりです。
| 項目 | 自然排煙 | 機械排煙 |
| 排煙方法 | 煙の浮力による自然の力 | 機械により強制的に排煙 |
| 予備電源 | 不要 | 必要 |
| 設置場所 | 屋外に面した部屋もしくはスペース | 屋外に面していない場所でも設置可能 |
| ダクトおよびダクトスペース | 不要 | 必要 |
| コスト | 低い | 高い |
| 保守管理の手間 | 少ない | 多い |
| 排煙の安定性 | 低い | 高い |
自然排煙設備と機械排煙設備は、どちらが優れているということではなく、建物や室内の環境、予算事情などにあわせた使い分けが必要です。
自然排煙設備は、コストの面だけを考えれば、機械排煙設備に比べて費用がかかりません。
また、ダクトスペースも不要なため、スペースに余裕がない場所にも設置可能です。
しかし、自然排煙設備は排煙口や排煙窓から排煙するため、外に面したスペースにしか設置できません。
そのため、窓がある部屋では自然排煙設備を利用し、窓のない部屋や廊下などのスペースには機械排煙設備を利用するといった使い分けをする必要があります。
また、煙の流れをコントロールする必要があるため、高層ビルでは機械排煙が主に用いられます。
機械排煙設備は保守管理の手間とコストがかかりますが、機械排煙設備でなければ設置できない場所もあるのです。
排煙設備の設置が必要な建物

以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、建物に排煙設備の設置が必要です。
| 〇床面積が500平米を超える特殊建築物・劇場、映画館、集会場など・病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設など・学校、体育館、図書館、スポーツ練習場など・百貨店、展示場、バー、飲食店、店舗など 〇床面積が500平米を超える3階建て以上の建築物 〇排煙上有効な開口部面積の合計が、床面積の1/50以下である居室 〇延べ面積が1,000平米を超える建築物の床面積が200平米を超える居室 |
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には排煙設備の設置は必要ありません。
| ・高さ31メートル以下の建物で、100平米以内ごとに防煙壁や防煙垂れ壁などで区画された部分・100平米以内に準耐火構造の壁がある病院やホテル、社会福祉施設などの施設 |
このように、病院やホテルなどでは排煙設備が不要な箇所があるケースも少なくありません。
また、学校や階段室、エレベーターなどでも排煙設備の設置は免除されます。
排煙設備の設置条件
排煙設備が必要な設置条件をみていきましょう。
排煙設備が必要な条件は、設備の種類によって変わります。
・自然排煙設備の設置条件
・機械排煙設備の設置条件
それぞれ説明します。
自然排煙設備の設置条件
| 条件1 | 排煙口の面積は防煙区画された部分の床面積の1/50以上の面積を有していなければならない |
| 条件2 | 排煙口で有効とされるのは天井面から80センチメートル以内の範囲まで |
条件3 | 排煙口には床面から80センチメートル以上150センチメートル未満の高さに手動解放装置を設置しなければならないもしくは煙感知器と連動する自動解放装置または遠隔操作方式による解放装置が必要 |
| ※防煙区画:火災時に煙が拡散しないよう防煙壁などで区画すること |
煙が広がることで避難の妨げとならないよう、間仕切り壁や垂れ壁などの防煙壁を設置します。
防煙区画は、建築の規模や用途ごとに建築基準法に定められています。
条件3の手動解放装置とは、手動で操作することで排煙口を開け煙を外へ排出させる装置です。
この装置は、非常時に多くの人が排煙口を解放できるような高さに限定されています。
機械排煙設備の設置条件
| 条件1 | 機械排煙における排煙機の能力は1分間に120立米以上、かつ、防煙区画の床面積1平米につき1立米の空気を排出する能力を有している |
| 条件2 | 電源が必要な場合は予備電源が必須で、高さ31メートルを超える建物の場合は、排煙設備の制御、作動状態を中央管理室にて実施できなければならない |
| 条件3 | 排煙口は不燃材料とし、排煙風道は不燃材料かつ木材などの可燃材料から15センチメートル以上離す必要がある |
このように排煙設備は、有事の際に生命を守る手段であることから、形式に関わらず条件が複数あります。
自然排煙設備、機械排煙設備それぞれについて、設置条件を満たしているか検証しましょう。
排煙設備は12条点検による定期検査が必要

排煙設備は、建築基準法第12条、いわゆる「12条点検」による検査が義務づけられています。
自然排煙設備は、12条点検のなかの特定建築物定期調査の対象となり、3年に1度検査を受けなければなりません。
機械排煙設備は、12条点検のなかの建築設備定期検査の対象となり、1年に1度の検査が必要です。
【自然排煙方式】特定建築物定期調査での検査
特定建築物定期調査での自然排煙設備に関する検査の内容は、主に下記のとおりです。
・排煙設備の設置の状況
・排煙設備の作動の状況
・排煙口の維持保全の状況
法令に適合した設置がなされているかを、目視および設計図書などにより確認します。
各階にある主要な排煙設備が、適正に作動するかどうかも検査の対象です。
排煙口が問題なく開閉するか、段ボールなどの物品により排煙の妨げになっていないか、また開閉レバーなどに損傷がないかなどを検査します。
【機械排煙方式】建築物定期検査での検査
建築設備の定期検査による機械排煙設備の検査では、排煙口・排煙機・排煙風道・手動開放装置などから構成される機械排煙設備が対象です。
検査内容については、主に下記のとおりです。
・排煙機の作動状況・風量の測定
・排煙口の設置状況・風量の測定
・手動開放装置の設置状況
・排煙風道・防火ダンパーの取り付け状況
・自家用発電装置の設置状況
機械排煙が有する排煙能力が設置条件を満たしているか、実際の作動状況や風量の測定をおこないます。
手動開放装置の設置状況(床面から80センチメートル以上150センチメートル未満の高さに設置されているか)や風量測定をおこないます。
火災時停電になっても稼働できるよう、適切に自家用発電機が設置されているかも重要な点検項目です。
排煙設備に関するよくある質問

ここでは、排煙設備に関するよくある質問を紹介します。
・排煙設備と換気設備の違いは何ですか?
・排煙設備の点検は義務ですか?
・建築基準法と消防法による排煙設備規定の違いは何ですか?
順にみていきましょう。
排煙設備と換気設備の違いは何ですか?
排煙設備は火事の煙を対象にしており、厨房や焼き肉などの煙を外に出す設備は、換気設備または排気設備といい、排煙設備とは区別されています。
排煙設備は、火災が発生した際に建物内の人々が火事の煙に巻かれることなく、安全に避難できるよう、煙を建物外に排出する設備です。
排煙設備は、緊急時の必要性が高いことから、建築基準法により一定の規模・用途の建物に対して設置が義務づけられています。
また、排煙設備は通路やエントランスホールなどにも設置が必要です。
一方、換気設備は室内の空気を屋外に排出する「排気設備」と、屋外から新鮮な空気を室内に取り入れる「給気設備」により構成されています。
室内の空気を入れ替える設備として、原則どの建物も設置が必要とされています。
排煙設備の点検は義務ですか?
排煙設備の点検は、建築基準法により義務づけられています。
排煙設備は、火災時に大量に発生する煙を屋外に排出することにより、建物内の人が安全に避難するための経路と時間を確保するなど、極めて重要な役割を果たすからです。
排煙設備には、「自然排煙設備」と「機械排煙設備」の2種類があります。
自然排煙設備は建築基準法第12条の「特定建築物定期調査」の点検対象であり、3年に1度の点検が必要です。
また、機械排煙設備は同じく建築基準法第12条の「建築設備定期検査」の点検対象であり、1年に1度の点検が義務づけられています。
建築基準法と消防法による排煙設備規定の違いは何ですか?
火災時に重要な役割を果たす排煙設備ですが、建築基準法と消防法では設置基準が異なります。
建築基準法では、火災時に建物内の人々が安全に避難できることを目的にしているのに対し、消防法では、消防隊員が安全かつ迅速に消火活動をおこなえることを目的としているからです。
そのため、建築基準法で問題なかった内容が消防に確認すると認められない、あるいはその逆もあり得ます。
たとえば、建築基準法では100平米以下の居室の内装、下地とも不燃とした場合には、排煙設備の設置が免除になりますが、消防法上の無窓階や地階では免除の対象とならないケースがあります。
また、地域によっては火災予防条例などで、無窓階など以外でも免除されない場合もあるため注意が必要です。
確認申請が不要な工事などで、告知の緩和を受ける場合には、消防への確認もあわせておこないましょう。
排煙設備の定期点検はテックビルケアにご相談ください

排煙設備には自然排煙設備と機械排煙設備の2種類があり、それぞれに設置する条件が異なり、義務づけられている点検の対象も同様に異なります。
さらに、建築基準法と消防法では同じ排煙設備でも設置の基準に違いがあるなど、分かりづらい点が少なくありません。
テックビルケアでは、特定建築物調査員や建築設備検査員など、建築防災に関わるプロフェッショナルが多数在籍しています。
排煙設備をはじめとする建築設備や消防設備に関するご相談は、ぜひお気軽にテックビルケアへお問い合わせください。