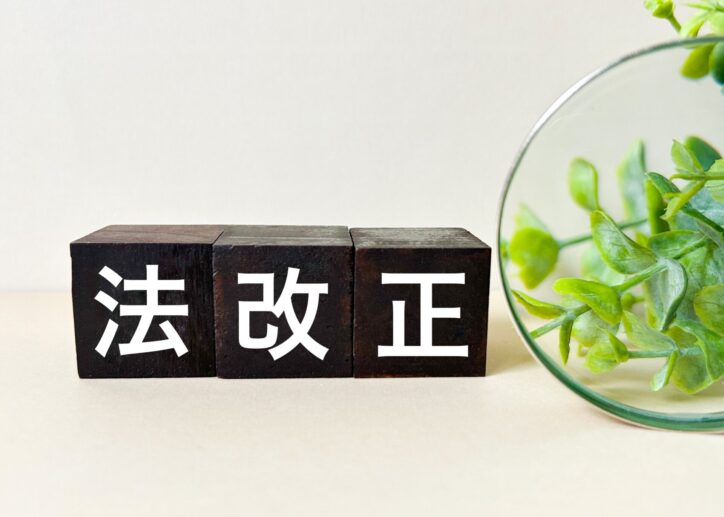特定建築物定期調査は、建築基準法第12条により定められている調査・検査のことで「12条点検」と呼ばれる点検のうちの一つです。
国は、デパートや娯楽施設・ホテル・病院など不特定多数の人が利用する施設の安全性を確保するために、建物の所有者または管理者に対して、定期的な点検や報告を義務づけています。
この記事では、以下の2点について分かりやすく解説します。
・定期報告が必要な特定建築物の対象となる建物
・特定建築物定期調査の概要や調査の流れ
特定建築物定期調査や報告などについての認識を高めましょう。
定期報告(特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備検査)特設ページはコチラ
定期報告が必要な特定建築物定期の調査とは?【12条点検】

特定建築物定期調査は12条点検の一つで、建築基準法第12条により定められている調査のことです。
建築基準法第12条では、対象となる特定建築物の所有者または管理者に対し、その建物の敷地・構造・設備などを定期的に調査し、特定行政庁※に報告しなければなりません。
| ※特定行政庁とは特定行政庁とは、建築基準法に基づいて建築の確認などをおこなう行政機関のことで、建築に関する事務を請け負う「建築主事」を置く、地方公共団体もしくはその長のことです。 |
12条点検は次の4つに分けられています。
・特定建築物定期調査
・建築設備定期検査
・昇降機等定期検査
・防火設備検査
それぞれ具体的に説明します。
特定建築物定期調査
特定建築物定期調査は、建物自体の老朽化や不具合などによって起こる、大きな事故や災害を防ぐためにおこなわれます。
調査の項目は主に次の5つです。
・通路や塀などを含む敷地や地盤
・基礎を含む建築物の外部
・屋上や屋根
・床・壁・天井などの建築物の内部
・避難施設
このように、建物自体やその周囲の環境を調査します。
続いて、調査実例をみていきましょう。
| 調査箇所 | 調査の実施例 |
敷地や地盤 | ・建物周囲の地盤が傾いていないか、陥没している部分がないか・敷地の塀に亀裂がないか・擁壁に水抜き穴が確保されているか・排水管から悪臭がないか |
| 建築物の外部 | ・外壁に剝がれたり、ひびが入っている箇所がないか・建物自体が傾いていたり、地盤沈下していないか |
屋上や屋根 | ・屋上のコンクリートに亀裂が生じていないか・防水用のモルタルが剥がれていないか・高架水槽がある場合、風雨に晒されてもろくなっていないか |
建築物の内部 | ・床や壁に、ひび割れや剥離している箇所はないか・地震の際に天井材が落下しないように止めてあるか・照明を妨げるものはないか |
避難施設 | ・通路等に、避難器具の使用を妨害するようなものが置かれていないか・避難時に妨げになるようなものや、可燃性が高いものがないか・非常階段などの手すりなどに、さびやが腐食がないか |
具体的には、目視による確認、建物の図面を用いて現物と比較する方法や、メジャーなどを使って長さを実際に測定しシミュレーションする方法などがあげられます。
建築設備定期検査
建築設備定期検査は、特定建築物定期調査が建物自体の検査対象であることに対し、建物に備え付けてある設備が検査対象です。
建築設備点検の項目は、大きく分けて次の4つ。
・給水・排水設備
・換気設備
・非常照明設備
・排煙設備
建物内部にある「利用する人が快適に過ごせるための基本的な設備」が対象です。
調査項目の実例をみてみましょう。
| 調査箇所 | 調査の実施例 |
| 給水・排水設備 | ・給排水に必要な受水槽や汚水槽、給排水管や高架水槽などに異常がないか、水漏れしていないか |
換気設備 | ・給排気口が適切な箇所にあるか、正常に動いているか・火器を使うような場所、または窓がない部屋の換気の状態は問題ないか・空調設備に異常や問題がないか・防火ダンパーの動作に問題はないか |
非常照明設備 | ・建物内にあるすべての非常照明の点検が必要・電池が内蔵されているものは、電池の寿命を確認する・設備の保守点検表の記載は正しいか・誘導灯が点灯しているか・自家発電設備がある場合は、保守点検票のチェックが必要 |
排煙設備 | ・排煙機の作動に問題はないか・可動排煙壁の作動に異常はないか・消防点検表の記載に問題はないか・排煙口から排煙する際に妨げとなるような荷物などが、高く積み上げられていないか |
目視による点検の他にも、特定建築物の定期調査で用いたような図面やメジャーを使った点検や、実際に機器や設備を作動させて動作を確認する方法、触れてチェックする触診などの方法があります。
昇降機等定期検査
昇降機等定期検査の項目は以下の4つです。
・エスカレーター
・エレベーター
・小荷物専用昇降機
・遊戯施設など
昇降機も大きな事故が起こる可能性が高いため、目視だけでなく触診や実際に稼働させることにより確認をおこないます。
昇降機点検では、目視や触診のほかにエスカレーターやエレベーターに乗っている際に異音がしないかの確認をする「聴診」も必要です。
昇降機の点検の実例としては、主に以下のとおりです。
| 調査箇所 | 調査の実施例 |
エスカレーターエレベーター | ・適正な速度か・制御器の作動は問題ないか・降下防止装置に異常がないか・エレベーターの操作盤やかごなどに問題はないか |
小荷物専用昇降機 | ・適正な速度か・制御器の作動は問題ないか・出し入れ口の開閉はいつもと変わらないか |
遊戯施設など | ・適正な速度か・制御器の作動は問題ないか・機関室の内外部に異常はないか・降下防止装置に異常がないか・操作盤やかごなどに問題はないか |
大きな事故につながらないよう、調査を念入りに実施しましょう。
防火設備検査
防火設備検査の項目は以下の4つです。
・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャーやそのほかの水幕を形成する防火設備
特に防火設備は、熱感知や煙感知の機能に異常がないかなどの慎重な調査が必要です。
| 調査箇所 | 調査の実施例 |
| 防火扉 | ・防火扉を動かす際に妨げるようなものはないか・防火扉が正しく動くか |
防火シャッター | ・防火シャッターを閉めるときに、妨げるものはないか・防火シャッターが動く際の装置に問題はないか・煙探知機や熱感知器の位置が適切か・危険防止装置が正常に機能するか |
耐火クロススクリーン | ・設置場所に妨げとなるものが置いていないか・危険防止装置の作動に問題はないか・危険防止装置の予備電源に問題はないか |
| ドレンチャーやそのほかの水幕を形成する防火設備 | ・周辺付近に散水を妨げるものはないか・ヘッドや開閉便などの部分に損傷がないか・散水用の貯水槽の中の水は充分な量があるか |
単純にシャッターが降りる、扉が動くというだけでなく、迅速に異常を感知し正しい信号が流れるかを確認する必要があります。
特定建築物定期調査の対象となる建物

ここでは、12条点検の中でも、特に建物自体の安全性を確保するための「特定建築物定期調査」の対象となる建物について解説します。
特定建築物定期調査の対象建物は、「政令で指定する建築物」と「特定行政庁が指定する建築物」に分けられます。
政令で指定する建築物は、特定の用途※で床面積が200平米以上の建築物が対象です。
| ※特定用途とは建築基準法で例示されている用途のことで、主に不特定多数の人が利用する用途や災害時などに援護が必要な人が利用する用途を指し、興行場、百貨店、集会場、図書館や美術館、遊技場、店舗、事務所、学校などがこれにあたります。 |
特定建築物定期調査の対象となる建物(政令指定)
| 対象の建物・施設 | 規模および位置など(いずれかに該当するもの) |
|---|---|
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など | ・3階以上の階にあるもの ・客席の床面積が200㎡以上のもの ・地階にあるもの ・主階が1階にない劇場、映画館、演芸場 |
病院、有床診療所、ホテル、旅館、就寝用福祉施設 | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が300㎡以上のもの ・地階にあるもの |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 | ・3階以上の階にあるもの ・床面積が2,000㎡以上のもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店公衆浴場、物品販売業を営む店舗 | ・3階以上の階にあるもの ・2階の床面積が500㎡以上のもの ・床面積が3,000㎡以上のもの ・地階にあるもの |
参照:国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」
次に、特定行政庁が指定する建物ですが、特定行政庁によってその基準が異なります。
東京都を例にとってみると、以下の条件を満たす建物が対象です。
・学校もしくは学校に付属する体育館で、床面積が2,000平米以上の建物
・5階以上で延べ面積が2,000平米以上の事務所や、それに類する建物、また3階以上の階にあって床面積が1,000平米以上の建物
また、東京都では、地下街や場外車券売り場なども対象です。
共同住宅であるマンションが特殊建築物に含まれるかも、各自治体によって異なります。
所有、または管理している建物が存在する自治体のサイトなどで、必ず情報を確認しましょう。
特定建築物定期調査の概要

特定建築物定期調査の概要について解説します。
・特定建築物定期調査の定期報告が必要な頻度
・特定建築物定期調査が可能な資格者
・特定建築物定期調査を怠った場合の罰則と危険性
・特定建築物定期調査の費用相場
さらに詳しく説明します。
特定建築物定期調査の定期報告が必要な頻度
特定建築物定期調査の点検自体は、3年以内ごとに実施が定められています。
ただ、こちらについても報告の時期などは行政ごとに決まっているため、各自治体の情報を確認しましょう。
たとえば、横浜市の点検・報告の例をみてみると「劇場や公会堂・病院など」の点検は、令和3年度を起点に3年ごとの周期で5月〜8月が報告の期間となっています。
同じように「百貨店や馬券投票所など」の点検は、令和2年を起点として3年ごとの周期で5月〜8月というように報告の期間が決まっています。
参照:横浜市「定期報告の周期」
報告書の様式は、ほとんどの自治体のサイト上に掲載されているので、そちらを利用しましょう。
特定建築物定期調査が可能な資格者
特定建築物定期調査は建築基準法により、以下のいずれかに該当する人だけが実施可能と規定されています。
・一級建築士
・二級建築士
・建築物調査員資格者証の交付を受けている者
基本的には、点検・報告を請け負っているとしている会社に依頼することが一般的です。
特定建築物定期調査を怠った場合の罰則と危険性
建築基準法101条により、特定建築物定期調査を怠った、あるいは虚偽の報告をした場合には100万円以下の罰金刑が科せられます。
特定建築物定期調査を実施しなかった場合、建物自体や周辺に異常が生じても気づくことができません。
結果、外壁の剥落や道路の陥没、金属の腐食による有害物質発生、避難経路の不整備による二次災害などの、人命に関わる大きな事故につながる可能性があります。
事故が起こってからでは取り返しがつかないため、必ず有資格者による定期点検をおこないましょう。
特定建築物定期調査の費用相場
特定建築物定期調査の費用相場(行政への届出手数料・出張費は別途)を紹介します。
ただ、規模や調査の内容などにより費用は変わるため、一つの目安としてご覧ください。
| 建物の用途 | |||
| 延べ床面積 | 共同住宅 | 事務所・病院・福祉施設 | ホテル・旅館・店舗等 |
| ~500平米 | 40,000円(税別) | 50,000円(税別) | 60,000円(税別) |
| ~1,000平米 | 50,000円(税別) | 65,000円(税別) | 75,000円(税別) |
| ~2,000平米 | 65,000円(税別) | 75,000円(税別) | 85,000円(税別) |
| ~3,000平米 | 75,000円(税別) | 85,000円(税別) | 100,000円(税別) |
| ~5,000平米 | 85,000円(税別) | 120,000円(税別) | 135,000円(税別) |
| 5,000平米~ | 別途ご相談ください | ||
参考までに、テックビルケアの建物タイプ別の料金体系は以下のとおりです。
特定建築物定期調査の流れ
特定建築物定期調査を依頼して、報告書を提出するまでの流れは以下のとおりです。
・調査会社を決める
・調査会社と打合せをする
・特定建築物定期調査を実施する
・報告書を作成し特定行政庁へ提出する
・「報告済証」が発行される
それぞれ詳しくみていきましょう。
調査会社を決める
点検の時期が近づくと、特定行政庁から検査の通知書が届くことが一般的です。
しかし、特定行政庁によって対応が異なるため、必ず通知が届くとは限りません。
通知が届かなくても調査ができるように、調査時期は必ず把握しておきましょう。
通知書が届く、または調査の時期が来たら調査会社を決めます。
建物の安全に関わる重要な調査であるため、資格者を有する会社であることはもちろん、経験や実績が豊富な会社に依頼しましょう。
調査会社と打合せをする
調査会社が決まったら、建築平面図や設備の図面、面積記載図などを準備して調査会社に渡し、調査の日時などを決めます。
特定建築物定期調査を実施する
実際に調査を実施します。
基本的に立ち会う必要はありませんが、質問などに対応できるよう連絡だけは取れるようにしておきましょう。
報告書を作成し特定行政庁へ提出する
調査終了後、調査会社が作成した報告書を確認し、署名・押印します。
そのまま調査会社に渡せば、代わりに特定行政庁に提出してもらえます。
「報告済証」が発行される
報告が完了すると、2〜3カ月後に「特殊建築物定期調査の報告済証」が発行されます。
建物の入り口付近や利用者が見やすい位置に掲示することで、建物を利用する人に安全性を伝えることができます。
出典:制度の概要・目的「公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター」
特定建築物定期調査は経験と実績のテックビルケアへお任せください!

特定建築物定期調査は、建物自体やその周辺の安全を維持するために必要不可欠です。
調査をおこなわなければ異常に気づかず大きな事故に発展するリスクがあります。
未然に事故を防ぎ、安心・安全を確保するためにも特定建築物定期調査は必要です。
特定建築物定期調査は、建築防災のプロフェッショナルであるテックビルケアへぜひご相談ください。